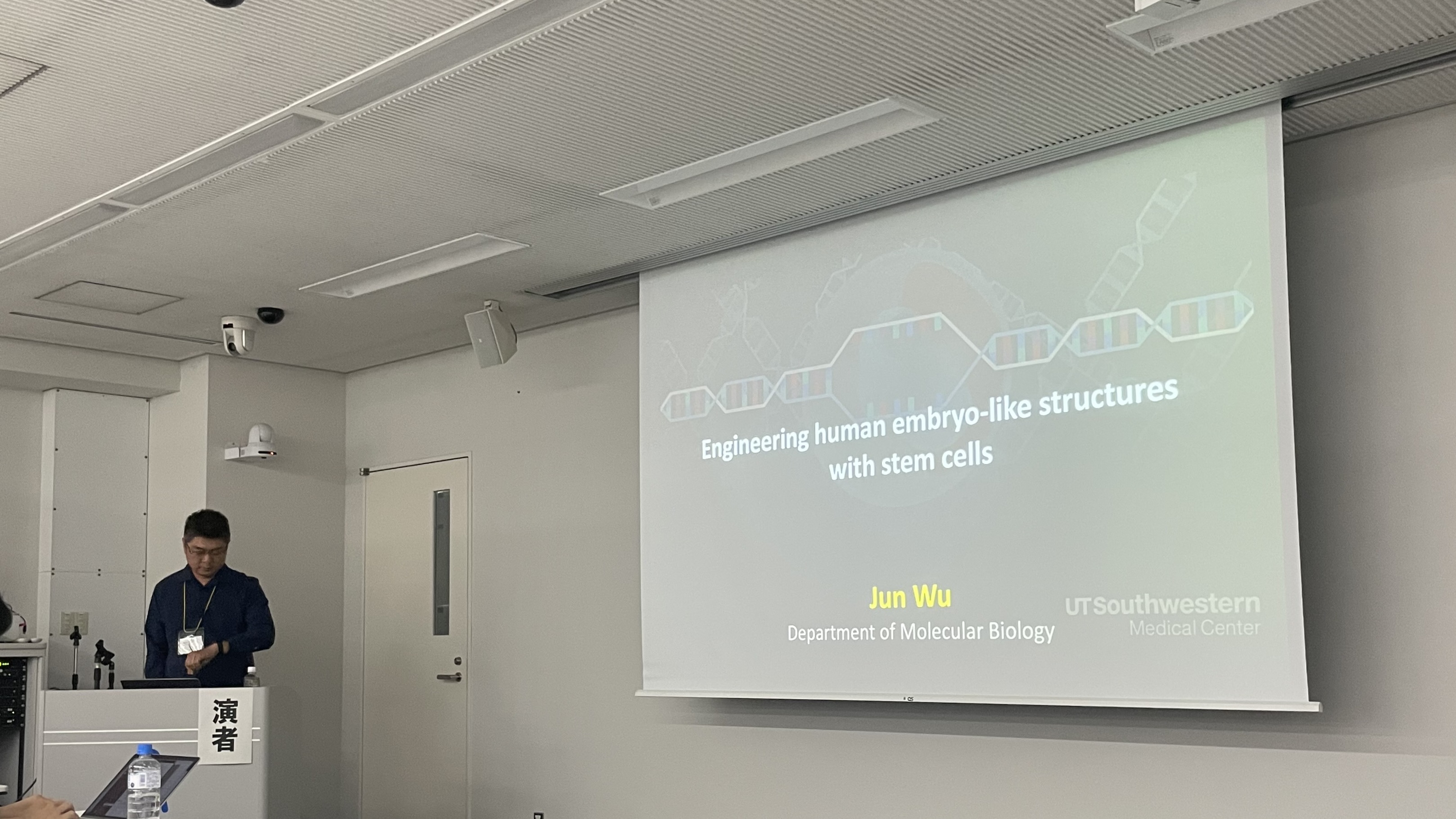第1回若手勉強会を開催いたしました。
京都大学 iPS細胞研究所 CiRA講堂にて、第1回若手勉強会を開催いたしました。
当日は、若手研究者55名を含む計67名の方々にご参加いただきました。
ベストプレゼンテーション賞は、以下の3名に贈られました:
- 松若 正篤さん(理化学研究所・井上班)
- 平岡 毅大さん(大阪大学・伊川班)
- 前川 瑠里さん(東京大学・太田班)
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!
以下、受賞コメントを掲載いたします。※先着順に掲載
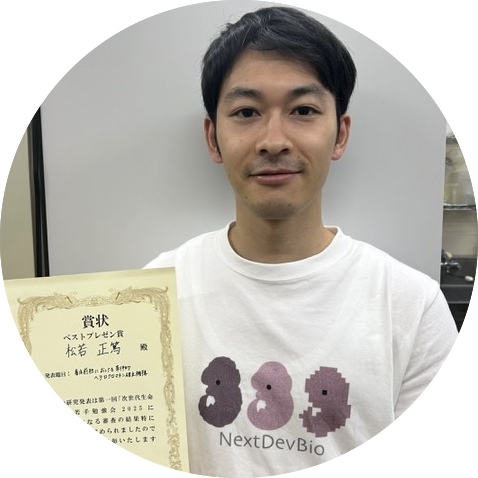 松若 正篤さん(理化学研究所・井上班)
松若 正篤さん(理化学研究所・井上班)
Q1. 略歴(大学、大学院、現職)
A1. 1997年東京生まれ。2021年に東京農業大学生命科学部(尾畑ラボ)を卒業。現在は、理研IMS 疾患エピゲノム遺伝研究チーム(井上梓ラボ)大学院生リサーチアソシエイト、兼、東京都立大学大学院生命科学専攻博士後期課程2年としてマウス初期胚でヒストン修飾を中心にエピジェネティクスを研究しています。
Q2. 今回受賞した研究の「クエスチョン」や「目的」について簡単に教えてください
A2. 胚は着床後発生に向けて、数千もの発生関連遺伝子群に条件的ヘテロクロマチンを形成し、一括して抑制状態を構築しています。こうした抑制機構がどのようにして胚盤胞までに確立されるのか?その詳細な分子機構とその生物学的意義の解明を目指して研究しています。今回は、ヒストンH2AリジンK119モノユビキチン化(H2Aub1)とその蓄積を担うポリコーム抑制複合体1(PRC1)に着目して、H2Aub1がどのように発生関連遺伝子に確立され、条件的ヘテロクロマチンの確立に寄与しているのか?といった疑問の解明に取り組んでいます。
Q3. 研究のどこに面白さを感じますか?
A3. まず、日々の実験やデータ解析から大小様々な発見ができる点が面白いと思います。世界で自分しか知らない結果を得る度に、現代の知識の縁を広げている気がして楽しさを感じます(もちろん残念な気持ちになる時もありますが)。あとは、論文発表を通して興味深い発見を他の研究者に共有できる点も面白いと感じます。そのため、シンプルな証明や納得感のあるロジックが詰まったエレガントな論文を書きたい!といつも考えています。
Q4. 本領域が終了する5年後は何をしていると思いますか?
A4. 私は来年に学位取得予定なので、5年後はアメリカかヨーロッパのどこかでポスドクをしているのではないかと思います。着床後ヒト胚モデルを用いたエピジェネティクスの研究にも興味があるので、vivoマウス胚×vitroヒト胚モデル×エピジェネティクスといったキーワードで研究を進めているかもしれません。
 平岡 毅大さん(大阪大学・伊川班)
平岡 毅大さん(大阪大学・伊川班)
Q1. 略歴(大学、大学院、現職)
A1. 2010年東京大学医学部医学科卒業し、医師免許取得。初期研修二年間の後に2012年東京大学産婦人科へ入局し、関連病院で勤務。2014年に東京大学大学院医学研究科へ入学し博士課程。廣田泰先生(現産婦人科教授)の研究室にて遺伝子改変マウスを用いた着床研究に従事。また、脱細胞化組織を用いた子宮再生研究にも従事。2017-2019年日本学術振興会特別研究員。2018年学位取得(医学博士)。2019-2022年再び産婦人科臨床医として勤務。2022年7月より大阪大学微生物病研究所伊川正人教授研究室にて体外子宮システムの樹立による体外での着床の再現研究に従事。特任研究員ののち特任助教。2025年7月より東京大学産婦人科の関連施設である大森赤十字病院産婦人科に勤務しつつ、東京大学届出研究員として研究に従事。臨床業務に従事しつつ、大学院生の指導も行っています。
Q2. 今回受賞した研究の「クエスチョン」や「目的」について簡単に教えてください
A2. 胚の「発生」については様々なモデルが報告されてきましたが、「着床」すなわち接着・浸潤・発生の全ステップを同時に生体内と同じレベルで再現したモデルは、マウスでさえもまだ無いと感じていました。「なぜ体外で着床を忠実に再現するのが難しいのだろう」というクエスチョンと、「生体内と同レベルの着床を体外で再現したい」という目的が研究のきっかけでした。クエスチョンへの私なりの答えは「胚の受け手側であるモデル子宮が不完全だから」というものでした。そのため、「真正の子宮組織を用いれば真正の着床が再現できるのではないか」という仮説のもとに実験が始まりました。
Q3. 論文で苦労した点は?
A3. 組織培養が可能な厚みの限界値が一般的に約400μmだそうで、子宮全体の厚みを考慮すると、子宮内膜の単離が必須でした。しかしこの、子宮内膜の管腔側(内腔、着床する側)を傷つけずに単離する方法を確立するのが大変でした。酵素を用いない外科的単離が最適と考え試行錯誤が始まりましたが、その手技を確立するのが大変でした。最初は1検体につき2時間くらい実体顕微鏡と向き合っていましたが、本気で吐きそうになりました(笑)(トレーニングの結果、最終的には15分くらいで完遂できるまでになりましたが)。また、単離した子宮内膜片に胚を載せる操作も、通常の胚操作と違ったトリッキーさが必要だったので、その手技の確立にも苦労しました。そのほかにも、培地組成や酸素供給の方向、デバイスのスペックなど、パラメーターが多すぎて、どこから手を付けていいのか分かりませんでした。帰りのバスで思いついたことをスマートフォンに片っ端からメモし、翌日に即試す、ということを繰り返していました。しかしながら何をいくら試しても接着も何も再現できず、心が折れそうな日々が続きましたが、ある日初めて胚の接着が再現できたときには思わず声が出ましたね(他の要素が整ったなかでのエストロゲン濃度調節が決め手となりました)。ただし、接着が再現できたあとも、その先の発生の再現にはさらに大きな障壁がありました。従来の胚単体の発生培養を自分で再現したうえで、現在の着床培養系と何が違うのか、あれこれ考える日々が続きました。色々な検討を行った結果、結果的に浸潤とE5.5相当までの発生を再現性をもって誘導できる条件を発見できてよかったです。このように自分なりに色々な困難と向き合ってきましたが、最終的に論文としてまとめることができたのは、何よりもラボの皆さんが日々支えてくださったのが一番大きかったと思います。本当にありがとうございました。
Q4. 本領域が終了する5年後は何をしていると思いますか?
A4. 今回伊川先生の研究室で基礎研究の楽しさを存分に教えていただきましたが、日々の臨床で出会うクエスチョンが研究のきっかけとなることはよくあるため、臨床医としてのアイデンティティーも大切にしたいと思っております。現在大森赤十字病院で勤務していますが、その後は東大に戻る予定になっており、臨床をしつつ後続(大学院生)の基礎研究指導をしていると思います。体外子宮システムを確立した身としては、体外での胎盤組織形成が夢なので、もしかしたら臨床の合間に自ら手を動かして実験しているかもしれません。
 前川 瑠里さん(東京大学・太田班)
前川 瑠里さん(東京大学・太田班)
Q1. 略歴(大学、大学院、現職)
A1. 2024年 東京大学総合文化研究科 修士(太田ラボ)卒業。現在、東京大学 工学研究科 先端学際工学専攻 博士課程1年
Q2. 今回受賞した研究の「クエスチョン」や「目的」について簡単に教えてください
A2. ジョージア工科大学の高山教授のもとで肺オルガノイドの研究に携わっていた際、三次元培養モデルが「基礎研究におけるメカニズムの解明」から「創薬スクリーニング」へと応用される過程に、ギャップが存在していることを実感しました。具体的には、従来のオルガノイドはサイズや形状のばらつきが大きく、また薬剤の浸透性やハイスループット対応といった観点から、スクリーニングに最適化されているとは言い難い状況にありました。このギャップを埋めるには、サイズの均一性が高く、薬剤浸透性に優れ、かつ数万種の化合物に対応できるような大規模な三次元モデル培養系の構築が不可欠であると考えるに至りました。そうした背景から、今回はマイクロ流体技術を活用し、小型かつ均質な三次元細胞モデルをカプセル内で大量に培養できるシステムの開発に取り組みました。
Q3. 研究のどこに面白さを感じますか?
A3. 私は、生命現象を解明するための革新的な技術を自らの手で創出することに、大きな面白さを感じています。その背景には、シドニー・ブレナー博士の有名な言葉 ‘Progress in science depends on new techniques, new discoveries and new ideas, probably in that order.’に深い共感を覚えた経験があります。科学における進歩は新しい技術の登場によって突如として見えなかった現象が見えるようになり、そこから発見やアイデアが次々と連鎖的に生まれるというのは自分の実感にも一致します。自ら生み出したツールが、他の研究者の問いや発見を支えるプラットフォームになること、そこから新しい研究分野が生まれる未来を思い描くことが研究を続ける上での大きな原動力になっています。
Q4. 本領域が終了する5年後は何をしていると思いますか?
A4. 胚発生や人工臓器分野を支える技術をつくり海外でスタートアップに入る、もしくは自分で仲間と会社を作っている気がします。その時に手元に自分が主導できる未開拓の分野があった際はその分野自体を学問として追求し、広めていくためにアカデミアにポストを残し次の10年後の産業になるような技術や発見を積み重ねて行きたいです。