計画研究班 A01-1生命を創発する多能性幹細胞の樹立
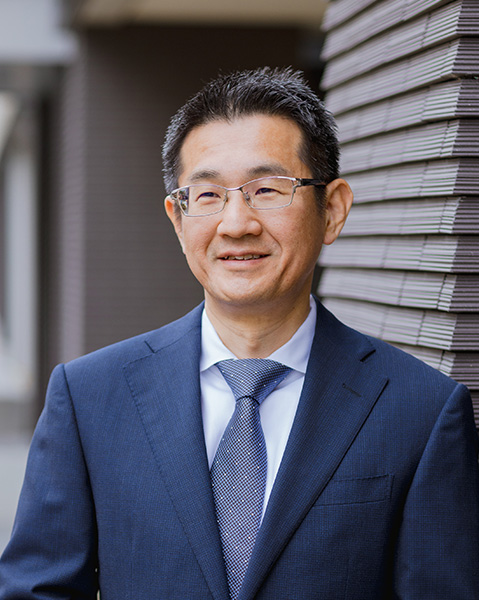
私たちは多能性幹細胞からin vivo胚によく似たin vitro胚モデルを作製できることに成功しました。しかし、現存のin vitro胚モデルは着床後の発生を部分的に再現するのみで、やがて異常をきたし、発生を停止します。この一因として、in vitro胚モデルの起点となる多能性幹細胞がin vivo胚と同等のエピゲノムを維持できないという問題があると考えます。そこで本研究では、ヒトやモデル動物を用いて、多能性幹細胞とin vivo胚を構成する細胞の詳細な比較解析を実施し、in vivo胚のエピブラストと同等の性質を持つ多能性幹細胞の新規培養系の確立を目指します。新規開発した多能性幹細胞を起点としたin vitro 胚モデルの構築を試み、生命創発の構成的理解に貢献します。
| 2024年 | 京都大学iPS細胞研究所 教授 |
|---|---|
| 2022年 | 京都大学iPS細胞研究所 准教授 |
| 2015年 | 京都大学iPS細胞研究所 講師 |
| 2007年 | イギリス ケンブリッジ大学 Wellcome Trust-MRC幹細胞研究所 ポスドク (EMBO、Herchel Smith、Hughes Hall、さきがけ研究者) |
| 2007年 | 神戸大学大学院医学系研究科博士課程修了 博士(医学) |
| 2002年 | 理化学研究所 発生・再生科学総合研究センター |
| 1998年 | 神戸大学医学部附属病院(第二内科)・西脇市立西脇病院(内科) |
| 1998年 | 神戸大学医学部卒業 |
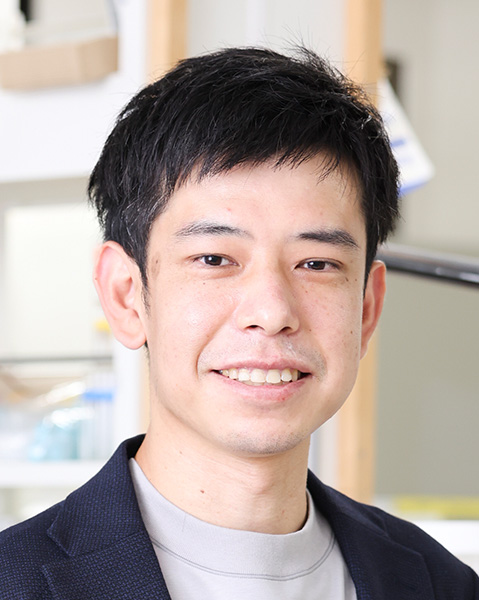
ヒト細胞を用いた研究はヒト胚発生の理解に直結する一方で、ヒト胚を用いた評価、あるいは動物胚を用いて動物性集合胚を作製し、動物体内で長期に渡って発生・評価するには倫理的な制約があります。そこで本研究ではモデル動物 (マウス、ラット、ウサギ、ブタ、非ヒト霊長類等) の多能性幹細胞に本計画班で開発する新規の培養系を適応し、動物胚を用いて個体発生能を厳密に検証します。また様々な動物種を扱うことで多能性やその維持機構における種ごとの違いおよび種を越えて共通する分子メカニズムを明らかにし、生命創発の根源に迫ります。
| 2025年 | 自然科学研究機構 生理学研究所 教授 |
|---|---|
| 2021年 | 東京大学 医科学研究所 特任准教授 |
| 2017年 | 自然科学研究機構 生理学研究所 助教 |
| 2013年 | イギリス ケンブリッジ大学 Gurdon Institute ポスドク (海外学振、上原財団) |
| 2012年 | 東京大学 医科学研究所 ポスドク |
| 2010年 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 修了 博士(生命科学) |
| 2005年 | 信州大学 繊維学部 卒業 |
計画研究班 A01-2ヒト幹細胞を用いた着床期胚発生機構の構成的理解

着床期は、哺乳類の初期胚が器官形成へと向かうダイナミックな形態変化を開始する、重要な時期です。しかしヒトでは、この過程が子宮内で進行するため直接的な観察が非常に困難であり、さらに倫理的な制約も相まって、ヒト着床機構の多くはいまだ謎に包まれています。本研究では、これまでの幹細胞を用いたヒト胚盤胞モデル(ブラストイド)の作製や、胚・胚体外組織のイメージングを通して、着床前胚の発生機構を明らかにしてきた知見を基盤とし、ヒト着床期における発生過程の可視化と、着床期胚の形態変化を制御するメカニズムの解明に取り組みます。これにより、ヒト胚発生、生命創発を担う機構の理解を深めることを目指します。
| 2022年 | 東京大学 農学生命科学研究科 助教 |
|---|---|
| 2021年 | 東京大学 医科学研究所 ポスドク |
| 2020年 | イギリス エクセター大学 LSI ポスドク |
| 2015年 | イギリス ケンブリッジ大学 Wellcome Trust-MRC幹細胞研究所 ポスドク |
| 2015年 | 東京大学 医科学研究所 ポスドク |
| 2014年 | 東京大学大学院医学系研究科 修了 博士(医学) |
| 2010年 | 東京大学 農学部 獣医学専攻 卒業 |
計画研究班 A01-3ヒト幹細胞を用いた器官形成原理の構成的理解

器官形成期は、体の基本構造がつくられる重要な時期です。器官形成に関する研究は主に実験動物を用いて行われてきました。一方、倫理的な問題から、ヒトでの研究はあまり進んでいません。近年の幹細胞培養技術の発展により、ヒトの初期胚に類似した構造を試験管内で再構成することが可能になりつつあり、ヒト胚を代替しうる画期的なモデルとして注目を集めています。しかし、器官形成期の発生を忠実に模倣可能なヒト胚モデルは報告されていません。本研究では、オルガノイド培養技術、マイクロ流路デバイス、ゲノム編集技術などを駆使し、着床期から器官形成期のヒトの発生を試験管内で再現し、その制御機構の解明を目指します。
| 2023年 | 熊本大学 発生医学研究所 教授 |
|---|---|
| 2019年 | 東北大学大学院医学系研究科 准教授 |
| 2012年 | 東北大学大学院医学系研究科 助教 |
| 2010年 | 東北大学大学院医学系研究科 研究員 |
| 2010年 | 東京大学大学院理学系研究科 修了 博士(理学) |
| 2004年 | 東京大学 理学部生物化学科 卒業 |

| 2024年 | 東京科学大学 総合研究院 生体材料工学研究所 教授 |
|---|---|
| 2021年 | 東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 教授 |
| 2011年 | 東北大学 大学院工学研究科 准教授 |
| 2007年 | 東北大学 大学院工学研究科 助教 |
| 2006年 | 東北大学 大学院工学研究科 助手 |
| 2005年 | 東北大学 大学院工学研究科 修了 博士(工学) |
| 2001年 | 東北大学 工学部 分子化学工学科 卒業 |
計画研究班 A01-4マウス幹細胞モデルによる生命創発の再現と構成的理解
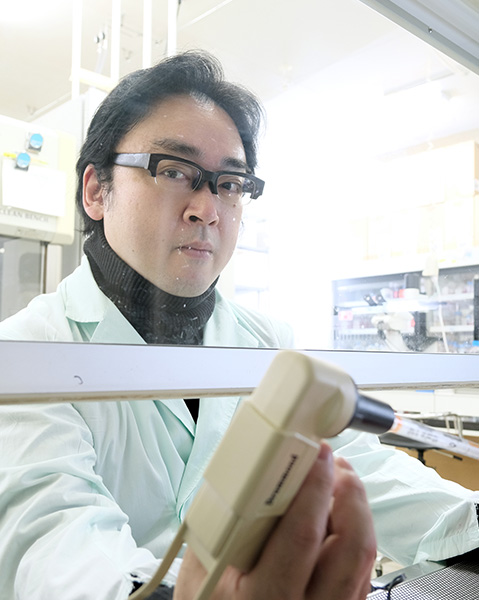
代表者
大日向 康秀
千葉大学大学院 医学研究院 講師
胚盤胞は、着床前エピブラスト、栄養膜、原始内胚葉の3種類の細胞系譜、数10個の細胞で構成される組織で、それぞれからは主に胚、胎盤、卵黄嚢が形成されます。着床前エピブラスト、栄養膜、原始内胚葉からはそれぞれ、ES細胞、TS細胞、PrES細胞が樹立されており、これらを組み合わせれば概念的には胚盤胞が再構成される可能性が示唆されますが、この幹細胞による生命創発の再現には世界のどの研究室もまだ成功していません。本研究では、3つ全ての幹細胞について、胚の細胞の性質を精密に捕捉し、3細胞間の細胞間相互作用を再接続可能とすることで、胚モデルに胚発生能をもたせること、言い換えれば幹細胞のみで人工胚を作製することに挑戦します。
| 2019年 | 千葉大学大学院医学研究院 講師 |
|---|---|
| 2015年 | 理化学研究所 生命医科学研究センター 研究員 |
| 2014年 | 山梨大学 生命環境学部 特任助教 |
| 2009年 | 科学技術振興機構 さきがけ研究者 |
| 2006年 | 理化学研究所 発生再生科学研究センター 基礎科学特別研究員 |
| 2003年 | 理化学研究所 発生再生科学研究センター 研究員 |
| 2003年 | 筑波大学大学院 農学研究科修了(農学) |

分担者
大瀧 夏子
千葉大学大学院 医学研究院 特任助教、科学技術振興機構 さきがけ研究者
初期胚構成細胞の単一細胞解析の結果から、胚盤胞内でのエピブラスト、栄養膜、原始内胚葉間の細胞間相互作用ネットワークを構築し、培養下で樹立した幹細胞候補株が形成する細胞間相互作用ネットワークとの類似性や差異を解析します。我々の研究室において新規に樹立する株について解析を行い、胚盤胞内ネットワークへの類似度が高い新規細胞株については、実際に胚盤胞への注入によってキメラ寄与能を評価します。これにより、幹細胞から作製した人工胚の発生能獲得に不可欠な細胞間相互作用の本質を明らかにし、生命創発機構への理解を深めることを目指しています。
| 2024年 | 千葉大学大学院医学研究院 特任助教 |
|---|---|
| 2024年 | 東京大学先端科学技術研究センター 客員研究員 |
| 2024年 | 慶應義塾大学大学院医学研究科 修了 博士(医学) |
| 2021年 | 千葉大学大学院医学研究院 特任研究員 |
| 2021年 | 東京大学先端科学技術研究センター 協力研究員 |
| 2016年 | 慶應義塾大学 医学部 卒業 |
計画研究班 A02-1父母性因子による発生保証機構

生命は精子と卵子の受精によって始まり、受精卵を構成しているのは精子と卵子それぞれに由来する父母性因子です。精子や卵子が形成される過程で父母性因子は一体どのように作られ、受精や胚発生でどのような役割を果たし、個体発生を成功させているのか、その全容は明らかにされていません。本研究では、母性因子による発生保証機構を明らかにすることを目的に、卵子が成長過程で母性因子を正しく獲得するための遺伝子ネットワークと母性因子が受精・発生に果たす役割を明らかにしていくことを目指します。
| 2017年 | 東京農業大学 生命科学部 教授 |
|---|---|
| 2016年 | 東京農業大学 応用生物科学部 教授 |
| 2010年 | 東京農業大学 応用生物科学部 准教授 |
| 2003年 | 東京農業大学 応用生物科学部 講師 |
| 1999年 | 群馬大学 遺伝子実験施設 助手 |
| 1999年 | 東京農業大学大学院 農学研究科 修了 博士(畜産学) |
| 1994年 | 東京農業大学 農学部 卒業 |

近年、精子形成期に付与される父性因子が受精後の胚発生や子孫の表現型に影響することが報告されつつありますが、そのメカニズムについては殆ど分かっていません。我々は、精子形成・機能不全により雄性不妊となる遺伝子改変マウス系統を多数有しています。本研究では、正常精子と異常精子を卵細胞質に直接注入する顕微授精により受精・発生させて影響を解析することにより、父性因子が次世代に与える影響を明らかにすることを目指します。
| 2012年 | 大阪大学 微生物病研究所 教授 |
|---|---|
| 2004年 | 大阪大学 微生物病研究所 助教授 |
| 2000年 | 米国ソーク研究所 博士研究員(2002年帰国復職) |
| 1998年 | 大阪大学 遺伝子情報実験施設 助手 |
| 1997年 | 日本学術振興会 特別研究員 |
| 1997年 | 大阪大学 大学院薬学研究科 修了 博士(薬学) |
| 1992年 | 大阪大学 薬学部 卒業 |
計画研究班 A02-2胚性転写プログラムによる発生保証機構
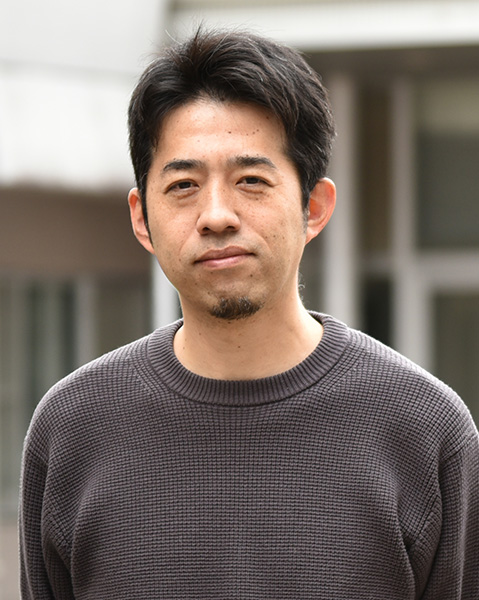
胚性ゲノム活性化に代表される初期胚特有の転写プログラムは生命創発に欠かせません。また、初期胚発生は刻一刻と進むため、ある時期に合成されたRNAやタンパク質がその合成期よりも後の発生期において重要な機能を果たすことが考えられます。近年では幹細胞を用いて初期胚モデルが構築されるようになりましたが、胚モデルは前段階にある発生過程を経ることなく作られます。この胚と胚モデルの違いは、胚モデルに長期発生能が見られないことの一因となっているかもしれません。そこで本研究では、初期胚特有の転写プログラムの制御機構および転写の下流にあるRNAやタンパク質の機能を明らかにすることで胚発生の理解と胚モデルからの生命創発に貢献します。
| 2022年 | 山梨大学 生命環境学部 准教授 |
|---|---|
| 2016年 | 九州大学 生体防御医学研究所 助教 |
| 2012年 | フランスIGBMC ポスドク(上原財団、HFSPフェロー) |
| 2011年 | 京都大学大学院生命科学研究科 修了 博士(生命科学) |
| 2005年 | 岡山大学 薬学部 卒業 |
計画研究班 A02-3エピゲノムによる発生保証機構
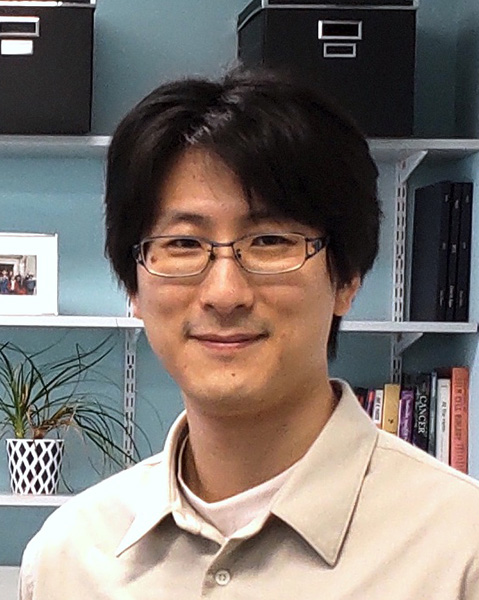
エピゲノムは発生や分化過程における適切な遺伝子発現制御に必須です。特に配偶子形成や受精、着床前発生の過程では、エピゲノムは極めてダイナミックに変動します。例えば卵では、体細胞には見られない特殊なエピゲノム構造が形成され、受精後にその大部分が消去されつつも一部は選択的に維持され、次世代の発生に寄与します。そして着床前発生過程では、体細胞型のエピゲノム構造が新たに形成されます。このようなエピゲノムの動態がわかってきた一方で、その制御機構や生物学的意義の理解は大きく遅れています。本研究では、マウスの卵形成から着床前発生過程におけるエピゲノムダイナミクスの機序と意義の解明を通じて、in vivo胚に備わる発生保証機構を明らかにします。ここで得られる知見は、配偶子や着床前発生を経ずに再構成されるin vitro胚モデルからの生命創発の試みに貢献します。
| 2022年 | 理化学研究所 生命医科学研究センター チームリーダー |
|---|---|
| 2019年 | 東京都立大学 理学部 客員准教授(兼任) |
| 2018年 | 理化学研究所 生命医科学研究センター Young Chief Investigator/上級研究員 |
| 2012年 | 米国ハーバードメディカルスクール ポスドク |
| 2011年 | 米国ノースカロライナ大学チャペルヒル校 ポスドク |
| 2011年 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 修了 博士(生命科学) |
| 2006年 | 東京都立大学 理学部 卒業 |
計画研究班 A02-4体細胞クローンで探る発生保証機構
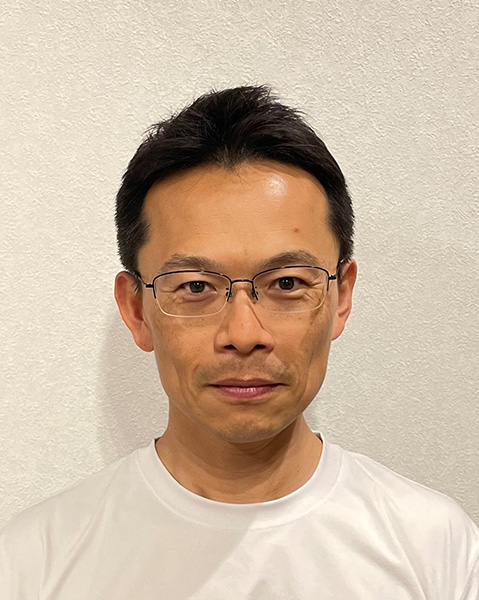
卵子の核を体細胞の核と入れ替えて作る「体細胞クローン胚」は、受精によってできる通常の胚と同じゲノム配列を持っています。しかし実際には多くのクローン胚が発生のごく初期、特に着床直後の段階で発生を止めてしまいます。幹細胞から作られる「胚モデル」でも着床直後に発生を停止するという同様の現象が見られることから、両者には共通した問題、特にエピゲノムの異常があると考えられます。本研究では、クローン胚に見られる発生停止や異常な表現型の原因となる新たなエピゲノム異常を明らかにすることで、正常な胚発生を支えるメカニズムである発生保証機構を解き明かします。そしてその知見を幹細胞研究に応用することで、胚モデルによる生命創発の実現に貢献します。
| 2017年 | 理研BRC 専任研究員 |
|---|---|
| 2015年 | 理研BRC 研究員 |
| 2012年 | ハーバード大学 ポスドク(HHMI、海外学振) |
| 2010年 | 理研BRC 基礎科学特別研究員 |
| 2009年 | 東京大学大学院農学生命科学研究科 修了 博士(獣医学) |
| 2005年 | 東京大学 農学部 獣医学科 卒業 |
計画研究班 A02-5次世代につなぐ発生保証機構

現在の日本では不妊症のカップルは5-6組に1組あると言われており、生まれてくる赤ちゃんの10人に一人が体外受精や顕微授精などの生殖補助医療により生まれています。これまでは受精を行うことで遺伝子情報がリセットされ完全な個体が生まれてくると考えられていましたが、私達はマウスを用いた実験で、これらの生殖補助医療により生まれた個体に世代を超えた異常が起こることを見出しました。生殖補助医療で用いられている技術は動物実験が不足していることが当初から指摘されており、ヒトの生殖補助医療により生まれている個体の長期予後や次世代に対する影響は未知のままです。そこで本研究では正常な受精と生殖補助医療により受精した個体の比較解析を行い、次世代につなぐ発生保証機構のメカニズムに迫ります。
| 2004年 | 京都大学大学院医学研究科遺伝医学講座分子遺伝 |
|---|---|
| 2003年 | 京都大学大学院医学研究科先端領域融合医学研究機構助教授 |
| 2000年 | 京都大学大学院医学研究科分子生体統御学講座・分子生物学助手 |
| 1996年 | 米国ペンシルバニア大学獣医学部ポスドク |
| 1996年 | 京都大学大学院医学博士課程修了(医学博士) |
| 1993年 | 京都大学 医学部 卒業 |
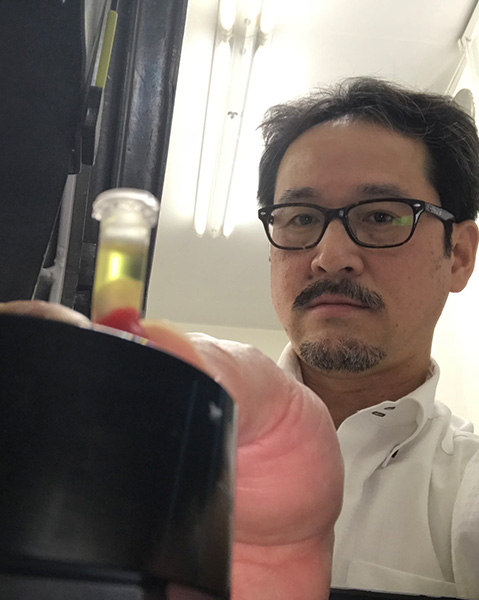
正常な受精と生殖補助医療により受精した個体の比較解析を行う為には、それぞれの個体に現れる症状(表現型)を網羅的に、かつ正確に調べる必要があります。私たちは国際共同研究プロジェクトである国際マウス表現型解析コンソーシアム (International Mouse Phenotyping Consortium: IMPC)に参画し、そこで使用される700項目以上(血算、血液生化学、形態、行動、感覚器、循環器、免疫、代謝、骨形態、剖検等を含む)を解析可能な世界基準のマウス表現型解析パイプライン (PL)を構築しています。本研究では、このPLを使用して生殖補助医療により生まれている個体、さらには次世代個体の網羅的表現型解析を実施します。加えて、新たな表現型解析法を開発して詳細な2次解析を行い、次世代につなぐ発生保証機構メカニズムの解明に貢献します。
| 2023年 | 理化学研究所 バイオリソース研究センター 室長 |
|---|---|
| 2018年 | 理化学研究所 バイオリソース研究センター チームリーダー |
| 2013年 | 理化学研究所 バイオリソース研究センター 開発研究員 |
| 2003年 | 国立遺伝学研究所 系統生物研究センター 助教 |
| 2002年 | 戦略的創造研究推進機構(CREST)研究員 |
| 1999年 | 日本学術振興会・特別研究員PD |
| 1998年 | 生物系特定産業推進機構研究員 |
| 1998年 | 総合研究大学院大学 生命科学研究科修了 博士(遺伝学) |
| 1996年 | 日本学術振興会・特別研究員DC2 |
| 1993年 | 山形大学 理学部 卒業 |
計画研究班 A03-1統合的データ解析による発生過程・幹細胞胚のモデル化と予測

1つの受精卵から個体を創発する胚発生では、遺伝子発現やエピゲノム状態の初期化と再編成、多様な細胞種への分化や自己組織化などのさまざまな現象を通じて、個体として機能する生命システムの構築と制御が行われます。その過程の理解のためには、重要な分子機構やパスウェイ等の各要素の研究に加えて、全体のシステムがどのように協調しているのかという大きなスケールでの理解が重要であり、さらには、得られた知見を用いて人工的に生命創発過程の生命工学操作を行うためには、その幹細胞胚の複雑な操作法の発見が必要です。本研究計画は、当学術変革研究の多様な研究者が得た知見やデータベース、本代表者の新規計測データなどを統合して「in silico デジタル胚」の構築を行い、胚発生を予測するシミュレーションとしての活用や、生物が持つ複雑な自己組織化のルールや発生保証機構の制御ルールの解明を通じて生命創発研究に貢献します。
| 2025年 | 大阪大学 微生物病研究所 教授 |
|---|---|
| 2024年 | 大阪大学 微生物病研究所 准教授 |
| 2022年 | Washington University in St.Louis Senior Scientist |
| 2017年 | Washington University in St.Louis Postdoc Researcher (JSPS海外特別研究員) |
| 2017年 | 東京大学 分子細胞生物学研究所 特任助教 |
| 2017年 | 東京大学 理学系研究科生物科学専攻 修了 博士(理学) |
| 2012年 | 東京大学 理学部生物化学科 卒業 |
計画研究班 A03-2均一で追跡可能な大規模胚モデルの作製と網羅的表現型解析

生命創発機構の解明に資するデジタル胚の開発には、迅速・安定な胚モデル作製と、有用なデータを計測するマルチモーダル解析法が必要です。しかし現在、幹細胞を用いたin vitro胚モデル構築と解析は、スピードとデータの接続性に欠けています。そこで本研究では、幹細胞由来のin vitro人工胚モデルに、遺伝子バーコードと独自開発の光バーコードを融合適用し、細胞系譜や分化動態を高精度に追跡・解析する計測基盤を開発します。これにより、時空間的な発生過程の可視化と定量化の実現を目指します。さらに、多重表現型解析と組み合わせることで、人工胚の構築精度を高め、デジタル胚の開発に資すると共に、初期発生の原理や破綻のメカニズム解明を目指します。
| 2025年 | 東京大学先端科学技術研究センター教授 |
|---|---|
| 2019年 | システム生物医学ラボラトリーディレクター |
| 2018年 | 東京大学先端科学技術研究センター准教授 |
| 2016年 | シンクサイト株式会社設立 共同創業者 |
| 2015年 | 科学技術振興機構さきがけ専任研究者 |
| 2014年 | 東京大学大学院理学系研究科助教 |
| 2013年 | カリフォルニア大学バークレー校機械工学科博士課程卒業 |
公募研究班(R8-R9)
総括班
| 評価委員(国内) | 小倉 淳郎 | 理化学研究所 バイオリソース研究センター 副センター長 |
| 評価委員(国内) | 塩見 春彦 | 千葉大学 次世代in vivo研究探索センター 特任教授 |
| 評価委員(国内) | 林 克彦 | 大阪大学 医学系研究科 教授 |
| 評価委員(国内) | 谷内江 望 | Univ of British Columbia, Biomedical Engineering, Professor |
| 評価委員(海外) | Austin Smith | イギリス Univ of Exeter, Living Systems Institute, Director |
| 評価委員(海外) | Alexander Meissner | ドイツ Max Planck Institute for Molecular Genetics, Professor |
| 評価委員(海外) | Maria-Elena Torres-Padilla | ドイツ Helmholtz Munich, Director of the Institute for Epigenetics and Stem Cells |
| 生命倫理委員 | 阿久津 英憲 | 国立成育医療研究センター 再生医療センター センター長 |
| 生命倫理委員 | 神里 彩子 | 国立成育医療センター 医事法制研究部 部長 |
学術調査官
| R7学術調査官 | 前田 優香 | 国立がん研究センター 腫瘍免疫研究分野 ユニット長 |
| R7学術調査官 | 堀口 道子 | 岡山大学 薬学部 大学院医歯薬学総合研究科(薬学系)再生治療薬学分野 教授 |